いくつも書いてる途中の原稿はあるにも関わらず、それらを仕上げる前に、今日はこれをどうしてもあげたいと思い、こちらのトピックで書きたいと思います。
先月6月26日、マサチューセッツ工科大学言語学教授スザンヌ・フリン教授が4年振りに来日とのことで、代々木にあるオリンピックセンターにてスザンヌ先生を迎えてのワークショップが行われました。
そこには、アメリカ ボストンからLEX AMERICAのエリザベス、LEX MEXICOのハビエル、マルタ、フェルナンダ一家、そしてヒッポファミリークラブの応援団である、東京大学の脳生理学者・酒井邦嘉教授、東京大学助教の梅島奎立さん、上智大学外国語学部教授の木村護郎クリストフ教授、ミュージシャンの坂田明さん、などなど、さまざまなところから多くのゲストを迎えてのワークショップでした。
このワークショップは26日に東京、そして29日には福岡でも行われました。
会を通しての感想は別投稿で書き途中のものがあるので、今回は割愛します。
そして先週木曜日。場を主催するフェロウなりたての人たちの会、新人フェロウの会は代表理事である鈴木堅史さん(ヒッポでは「けんちちゃんだ〜」というニックネーム)との懇談会でした。
そしてこの日はLEX MEXICOのハビエル、マルタ夫妻も参加してくださっていました。
けんちちゃんだ〜の話のなかには、メキシコヒッポの成り立ちを軽く触れる上で、25年前にけんちちゃんだ〜一家がアメリカでヒッポを伝えていたことにも触れていました。
実は、私は同時期に父の仕事で1年間カナダのトロントに住んでおり、当時フェロウだった両親はトロントでもアメリカでのプロジェクト同様ヒッポを広めたいなと奮闘していたのでした。
当時私は8歳。現地の小学校に通い、自分のことで精一杯、もちろん定期的な活動の場にも一緒に行っていましたが、親の苦労なんてつゆ知らず・・・
それが今回、私も新しい人にヒッポを伝えていく立場になって改めて、この当時のカナダ トロントでヒッポを広める活動をしていた両親が記録した「トロントレポート」を読んでいました。
けんちちゃんだ〜の話と、この「トロントレポート」すごく共通することもたくさんありました。そのなかで一つピックアップしたいと思うのが
アメリカでは、多民族がいるから、「英語」で国をまとめてきた、まとめている国。
そして、カナダ トロントも多民族多国籍、いろんな国の人がたくさんいる、ヒッポでいえば豊かな環境だけど、どこの建物にも「ここは多国籍文化、だから共通の言語『英語』で話しましょう」との張り紙。そして、母は「トロントレポート」のなかで、トロントは多民族、多国籍、いろんな言語がすごく身近にあるけれど、多言語を話せても嬉しくない人たちがたくさんいるということを感じていることに触れていました。
多言語がたくさん身近にあるから共通の言語「英語」でまとめてきた、そしてそういう考え方の人が8割いるアメリカ・カナダでこの「多言語を話そう!」というヒッポを広めるのと、基本的に「日本語」の単言語の島国、日本でこの活動を広めるというのは伝え方というか、響くところが違うのかなと感じました。
(アメリカでは2年半で29家族が入会し、4つのファミリーが生まれたそうです。カナダでは実質半年の活動期間であったこともあり、これから・・・というところでの帰国でした。)
なので、けんちちゃんだ〜にその旨を質問したんですね。
それに対して、けんちちゃんだ〜が話してくれたことは、
一言では言えない。けれど、スザンヌ先生が(ヒッポの活動を知った時に)感動したところ。人と人との繋がり。Kind hospitality。Compassionary(やさしさ)単なるやさしさでなくて、心から、この人と一緒にやりたい。人と人とのつながりがいい。言葉の説明もした。言葉には興味がある人が多かったけれど、人と人とのつながりに感動して入ったひとが多かったかな。(新人フェロウの)みんながやっていることと重なる。言葉以上の人と人とのつながりや、小さい子と多世代でやることに価値をもってくれた人。そこに気づいてくれるまでも何回も説明した。お母さんのように受け止め合う環境ということに感動したんじゃないかな。
ということでした。
共通の言語「英語」で一つの国家を作ってきた国の人たちにも、基本的に単言語の島国「日本」でもやはり中身は同じ「人」
「人」と「人」同士がお互いにやさしさを持って愛情深くお互いに心を寄せ合う。
そういえば、先月私が主催したワークショップ・講座の一連を通しての私の中での裏テーマが
「来てくれた人たちが、ここだったらどんな自分でも、どんな子供でも受け止めてくれる、居心地のいい場所だな」って感じて帰って欲しい
ということだったことも併せて思い出しました。
どうして多言語?どうして多世代?
講師の話をいただいたとき、私もずっと「多言語、多世代、多国籍が当たり前にある環境。どんな人に対しても目の前にいる人は紛れも無い『人』であって言葉や世代・国籍なんて肩書きにとらわれずに接していくのが当たり前に育ってきた。」というような旨を伝えてきたつもりでしたが、なんかもっとその言葉の深いところに潜れた気がしています。
だから多言語。心を開いて人と人がつながっていくことを大切にしている。
それにしても、スザンヌ・フリン教授は、30年も40年も前からアメリカという「みんな英語で話そう!」で国がまとめられてきたところで「多言語の環境の方が自然。多言語は知性をのばす。脳にもいい!」と研究して提唱するということはどんなにすごいことか・・・(スザンヌ教授のコメントhttps://www.lexhippo.gr.jp/what/supporter_detail12.php)
そして、14、5年前にボストンの地下鉄でヒッポの「Anyone can speak 7 launguages」というポスターを見て、ヒッポの活動を知ったときは本当に嬉しかったんだろうなあ・・・
そしてヒッポを知って、なんども日本で講演会をしていただいたり、酒井教授を紹介してくださったり、MIT・東大・ヒッポで共同研究が始まって、一昨年には研究成果を発表されて(東京大学プレスリリースhttps://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00003.html)
もちろん研究に主に携わってきた教授たちにも感謝です。
ですが、同時に、この40年以上もこの活動を続けてきてたくさん広げてきた日本全国・世界のヒッポメンバーたちにも大きく、感謝です。

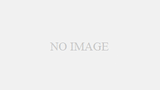

コメント